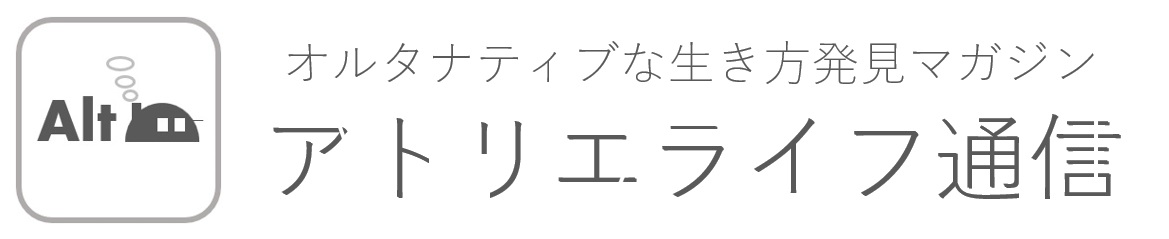SNSによってやりやすくなった施策のひとつがキャラクター運営。イベント単位ではなくデイリーでコストをかけずにキャラを転がしていける。また着ぐるみの場合は言葉を使うのが難しいが、SNSは自由自在に言葉を繰り出せる。くまもんなど有名どころはもちろん、他にも意外な所に10年選手が生息している。
その一例がカルビーが10年間運用しているXの非公式キャラクター「黒エビ」だ。非公式ゆえに自由に、特定の商品に関わらずに時に黒い発言もするキャラクターはじわじわとファンを増やしていた。徐々に高まってきた人気を受けて、昨年秋にSUZURI内のカルビー公式オンラインショップでグッズを発売した。
広告コピーもキャラクターの発言も、すべてはコミュニケーションなので相手と送り手との胸の内に共通して存在する何らかの気分やトピックをとっかかりにする必要がある。どのテーマを選び、それをどんな味わいのやりとりにするのか?日常生活にスッと素敵な解釈を与えてくれる存在は無敵になれる。
弊社がブランドコピーを担当した淡路ビーフも、そのブランドパーソナリティ設計という骨子を「肉付け」していく取り組みとして22年5月から「モーコ」というキャラクターを運営中。以前紹介した「くすぐり表現」を軸に、じわじわとコミュニケーションを積み重ねている。過去の投稿事例を8つのアプローチに分類して紹介してみよう。

キャラクターの転がし方:8つのアプローチ
くすぐり表現のアプローチ例①:嬉しい気分に薪をくべる
コピーライターの師匠は、広告コミュニケーションの基本は「相手の言ってほしいことを言ってあげること」と常々言っていた。キャラクターが人々に話しかける時も、ペインをネチネチ指摘するのではなく、うれしい気分をさらに膨らませる発言をすべき。
グッド モォ〜〜〜ニン。巷では今日は「土曜日」ってやつでニンゲンの大好物みたいね。よくわからんがおめでとう㊗️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) March 25, 2022
▲誰しも一番嬉しいのが「土曜日の朝」。牛目線でちょっとわからないながらも、一緒に喜んであげる。
グッド モォ〜〜〜ニン。連日のBBQ祭りでおつかれの人も多いでしょう。連休中は二度寝をする権利が憲法で保証されていますから、安心して二度寝をどうぞ💤 食べて寝て、憧れの牛になろう❗️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) May 4, 2023
▲連休=BBQ祭りという前提。そして、牛=憧れの存在という二重の前提ズラシからの発言。「食べてすぐ寝たら牛になる」といういにしえ構文を下敷きに。
くすぐり表現のアプローチ例②:ちょっとユーウツな気分をなぐさめる
1つ目と逆のアプローチだが、連休明けなど「誰もがユーウツ」なタイミングでは、ちょっと気を逸らして前向きにポジ転できるコミュニケーションがよい。
グッド モォ〜〜〜ニン。しかしアレだね、人類ってのは連休が好きだよね。そして毎度お決まりみたいに、連休が終わるとこの世の終わりみたいな顔になるね。ここでいいコトを教えておこうか。連休があるってことは、そのぶん次の平日が減るってことだ❗️人類よ、これがポジティブシンキングだ‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) October 9, 2022
▲一番つらいのは「連休明け」なので、連休明けの隠れメリットである「平日が一日少ない」ことを人類全体にリマインド。
グッド モォ〜〜〜ニン。連休明けは牛もツライ❗️正月休み明けの最初の土日を三連休にしてくれる「成人の日」に、アタシからノーベル平和賞を授与することに決めた‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) January 4, 2023
▲正月明けの成人式を含む3連休は毎年「ありがたい・・」と思える給水ポイント。その祝日に対して、勝手にノーベル賞を贈ってしまう暴挙。
グッド モォ〜〜〜ニン。イマイチ仕事のやる気が起きない時は、とりあえず雑務を淡々とこなしていくとリズムが出てくるかも•••というわけで、とりあえず反芻中❗️モーコ営業中‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) May 9, 2023
▲連休明けの仕事がはかどらない状態を解消するTipsを牛目線で。
くすぐり表現のアプローチ例③:焼肉ネタ
お肉のキャラクターなので、当然焼肉まわりのネタも転がしてみる。BBQ中に真似して言ってくれたらしめたもの。
グッド モォ〜〜〜ニン。ニクを焼いたときに煙が出ますが、アレがカロリーの正体です。だから焼肉はカロリーゼロ❗️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) May 16, 2025
▲サンドウィッチマン・伊達みきおの「カロリーゼロ理論」を焼肉に応用。
グッド モォ〜〜〜ニン。ここだけの話、リア充の「ジュー」はお肉を焼く時の「ジュー🥩」なのです❗️さっそくこの週末、リアジューしましょ‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) April 18, 2024
▲BBQに誘うポジティブなバカ口実を提供。まあ、アウトドアといえばそうなので、あながち嘘でもないのだが。
くすぐり表現のアプローチ例④:時事ネタと牛ネタを絡める
その時々で多くの人の関心が向かっている話題に乗っかるアプローチ。毎日の空気感に呼応してメッセージが組み立てられるSNSならではのコミュニケーション。
グッド モォ〜〜〜ニン。㊗️ドジャースがワールドシリーズ制覇❗️夢を叶えつづける大谷翔平選手の原動力といえばたっぷりの睡眠ですが、いい夢みるには羊🐏じゃなくて牛🐂を数えるべし。お腹いっぱい夢がみられます。しらんけど。
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) October 31, 2024
▲大谷選手=睡眠を大切にしている、という広く知られた事実を軸に、牛ネタへ展開。「羊を数える」といういにしえ構文を応用して遊ぶ。
グッド モォ〜〜〜ニン。メジャーリーグのワールドシリーズが盛り上がってますな。ドジャースといえば大谷翔平選手‼️ですが、外野手も内野手もこなして、スイッチヒッターで大事な時にセーフティバントもキメるエドマン選手も、いい味だしてる。
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) October 7, 2024
▲ワールドシリーズ前後にマルチな存在で大活躍したドジャースのエドマン選手をひきあいに、ブランドタグラインである「いい味だしてる。」の意味性を強化。
くすぐり表現のアプローチ例⑤:2-3回に1回はブランドメッセージを届ける
ブランドのことを語りすぎても押しつけがましくなるが、語らなすぎたらやっている意味がなくなるので、適切な頻度と温度感でブランドメッセージを語る。
グッド モォ〜〜〜ニン。いいものを食べたあと、しばらくお腹がしみじみとヨロコビを感じることがありますね。淡路ビーフのパーパスは「日本中の胃袋をハピネスで満たす」です❗️(ウソ)
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) March 11, 2025
▲脂っこすぎない淡路ビーフならではの食後の満足感を描写。その流れでメチャメチャそれっぽい(ありそうな)パーパスを宣言し、直後に否定。
グッド モォ〜〜〜ニン。春到来、ということはBBQシーズンも開幕❗️でっかい空の下で食べる淡路ビーフ🥩は格別で別格なのであーる‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) April 3, 2025
▲春到来の嬉しい気分に淡路島でのBBQを紐づける。よくある「格別」ではなく、「格別で別格」という反転リフレインで斬新な格別感を表現。
くすぐり表現のアプローチ例⑥:牛と人類のカルチャーギャップコメディでくすぐる
流暢に話すしモノゴトも分かっていそうだが、肝心なところはことごとく「カンチガイ」していることでカルチャーギャップコメディの楽しみを演出。
グッド モォ〜〜〜ニン。なんだか今朝はいろんな人から「おめでとう おめでとう」と言われるわ。ようわからんけど・・・ありがとう‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) January 1, 2023
▲そもそも「お正月」というものがよくわかっていない。所詮は牛なのだ。
794年にウグイスが鳴いたって話は教科書に載ってるくらい有名だけど、1300年の血統を持つわが但馬牛のご先祖はこのホケキョを聴いてたってことなのよね。圧倒的感慨❗️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) April 13, 2022
▲有名な歴史年号を知っているようで、根本的にカンチガイしている(のに全く気づいていない・・!)という滑稽な前提から一転、1300年の歴史と伝統を持つ但馬牛=淡路ビーフの価値に落とし込む。
グッド モォ〜〜〜ニン。平成レトロがブームだとか言ってたら、最近は「エドテック」が熱いらしい🔥秋頃には縄文レトロがきっと来る‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) February 7, 2025
▲これもわかっているようで何か根本的にわかっていない「所詮は牛」視点がどんどんエスカレートしていく様子を活写。
グッド モォ~~~ニン。「食べてすぐ寝たら牛になっちゃうわよ」ってママさん叱るけど、牛になるってランクアップだよね⁉️それをいうなら「牛になれるわよ!」でしょ。いい夢みて、起きたら夢も叶って、こんなに美味しい話は淡路ビーフにしかできん❗️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) June 11, 2022
▲「人類は牛をめざしている」という誤った前提から、勝手な話を展開し、さらに勝手に恩着せがましく話を終わらせる。
くすぐり表現のアプローチ例⑦:季節ごとの生活者の気分に寄り添いつづける
キャラクターを転がすことは、四季折々の生活者の気分に寄り添いつづけること。それによって、生活者の「お供」となる存在になれる。
グッド モォ〜〜〜ニン。新入生に告ぐ❗️勉強で大事なのは何よりも反芻。牛を見習いなさいっ‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) April 12, 2024
▲春は新入生に対して「謎の上から目線」で叱咤激励をとばす。牛の独特の食事法である「反芻」を取り出してきて遊ぶ。
グッド モォ〜〜〜ニン。モォ〜暑がとまらんっ☀️ノストラダムスが予言した「1999年 7の月、空から恐怖の大王が降ってくる」って、ゼッタイ紫外線のことだよね⁉️99年だと最近回復してきたオゾンホールがまだ大きかったし‼️今年の恐怖の大王もなかなか手強そう。みなさまご安全に〜
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) July 18, 2024
▲猛暑の夏のユーウツには「ノストラダムスの7の月の恐怖の大王」を「振り返って考えてみれば・・」的な愉快な捉えなおしで乗り切ろうとする。
グッド モォ〜〜〜ニン。今日も朝から山はシンフォニーホール状態。セミも土日くらいは休めばいいのに❗️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) August 4, 2023
▲8月の淡路島といえば「セミの大合唱」。味覚表現の「旨味と甘みのハーモニーが、もはやシンフォニー」にもかけながら、轟音を出すセミに人間的な配慮を求める。
グッド モォ〜〜〜ニン。無尽蔵に元気なセミの羽根ってあれ、ソーラーパネルじゃない⁉️雨の日はずいぶんと大人しいのが何よりの証拠❗️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) August 8, 2023
▲モーコはとにかくセミが嫌い。嫌いだからアレコレ考えて何かそれっぽい発見をしてしまう。
くすぐり表現のアプローチ例⑧:突拍子もないアングルから雑談を切り出す
キャラクターの仕事は生活者を日常から連れ出すこと。「どこから持ってきたん?」というようなアングルから急に話題を展開し始めることで、日常に彩を加える。そういえば犬もたまに「どこから拾ってきたんや?」っていう”お土産”を持ち帰る。
グッド モォ〜〜〜ニン。歯ブラシのCMで「Q.虫歯予防にはプラークコントロールが大事?」にいつも3%くらい「NO❗️」と答えるひねくれ者の歯医者さんがいますね。そういうものに、アタシもなりたい‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) May 23, 2023
▲これは30年前から使われている歯ブラシのCMのシンボリックデータ。今でも使われているが、そんなありふれたデータも見方によっては新たな発見がある。それによってキャラクター性を際立てる。
グッド モォ〜〜〜ニン。たまにはアカデミックな話を。英語の「RUN」という言葉は活用していくとラン→リャン→ランとなりますね。この過去形のリャン(RAN)ってのが巷で有名な「ランナーズハイ」の正体なのです❗️受験生、今日の入試にでるぞ‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) February 14, 2023
▲誰もが通ってきた学校カルチャーネタ。英語の「RUN」の活用とランナーズハイを掛け合わせることで「それっぽいけど全然ウソ」な気づきを発掘。
グッド モォ〜〜〜ニン。何とついにワープする方法を編み出してしまった❗️やり方は簡単、寝がけの牛数えを応用するだけ。朝起きたらそこで慌てて起きずに、目を閉じて精神統一。そしておごそかに牛を数える。気がつくと、なんと次の日にワープしている‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) September 19, 2022
▲以前紹介した「羊ではなく牛を数える」を応用研究して、翌日にワープするナンセンスな発明を披露する。
今週の週刊ワーケーション関西によれば、よいアイデアって「絡み合った問題を一刀両断」するアイデアなんだって❗️おいしいんだけど使いにくくて売れないどうしよう❗️って端切れ肉をまとめてグニュっと売り物に。ピンチを「ミンチ」に変えた人は天才‼️
— モーコ | 淡路ビーフ@アイドル見習い (@MoocoClumsyIdle) May 4, 2022
▲クリエイティブ発想法のネタを得意のお肉領域に転用する。すると、絶妙なダジャレが誕生。
▼この記事の内容はポッドキャストでも配信しています▼
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…
通りすがりの見知らぬ受け手とコミュニケーションするフックとして気づきが有効だが、もうひとつ「くすぐり」もある。チャーミングなくすぐりによってココロがほぐされて怒る人はいない。そしてロングエンゲージメントに向いている。キャラクター展開はこの「[…]
コト消費の主役は「体験消費」。これによって人は消費者から主人公になる。昨今話題の新種の体験価値を創出するアミューズメントパークはもちろん、コンテンツ視聴後のSNS上での考察など、あらゆる場面で体験が求められている。主人公たる人々に対しては「[…]
いにしえより伝わる古き善き、そして太き文脈を使うと間口と奥行を両立させた強いメッセージが打ち立てられる。「昔むかしあるところに」といった昔話構文の中には豊かな表現フックがたくさん埋まっていて、それを掘り起こせば速やかに意味伝達できる。さらに[…]