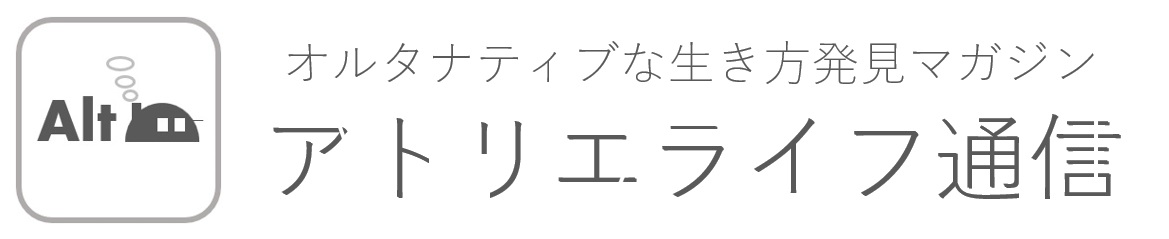通りすがりの見知らぬ受け手とコミュニケーションするフックとして気づきが有効だが、もうひとつ「くすぐり」もある。チャーミングなくすぐりによってココロがほぐされて怒る人はいない。そしてロングエンゲージメントに向いている。キャラクター展開はこの「くすぐりコミュニケーション」がコアエンジン。
優れた漫画・アニメなどの豊かな土壌に育った日本人は「Cawaii」の感性が豊か。キャラはもちろんロボットもおじさんも何でもかわいがって無害化してしまう。「キモかわいい」などは立派な感情のイノベーションだ。よってブランドコミュニケーションにおいても「くすぐり表現」は最強の武器のひとつ。
くすぐり表現によってブランドと生活者は「仲良く」なれる。「ほっこり➡にっこり」という心地よい感情が自然と湧きおこり、好ましい感情記憶とともにブランド記憶が塗り重ねられていく。気づきを与え続けるのは大変だが、くすぐり続けるのは可能なので是非検討したいアプローチである。
ほっこり➡にっこりで「仲良し」になる、くすぐり表現のアプローチ例
事例①:人間臭さでほっこりさせるポッキー&プリッツの日
「くすぐり表現」で秀逸だったのが、16年11月11日のポッキー&プリッツの日。年に一度のハイライトな一日を「一年で一番つらい日のはじまりです」と語るプリッツ。同じグリコ同士、せっかく並びで記念日になっているのに、街のポスターも公式からの扱いもポッキー一色で完全に「じゃない方芸人」扱い。
ポッキー&プリッツの白眉は、定番のお菓子が「スネる」という極めて人間くさい感情を吐き出したこと。プリッツのパッケージに目や口を描いたわけではないのに、うなだれる様子が想像できてしまう高度な擬人化アプローチ。ブランドコミュニケーションにおいて珍しいネガなベクトルに振り切ったのが奏効。
SNSで感度を増した「共感感性」の視点でもポッキー&プリッツは優れている。街ゆく人々のなかで生れながらの主役キャラはほぼいない。ほとんどが目立たないし「じゃない方扱い」されることも度々ある。だから多くの人がスネるプリッツに強い共感を覚えてしまい、応援したくなる。
事例②:ファミマの涙目シール
低関与商材の場合、売り場の気分で買われるので「ちょっといいことした気分」は付加価値となり購買を促進する。ファミマはおにぎりの値引き品に情緒的に訴求する「涙目シール」を導入し、廃棄される食品を助けるために買うという行動設計をした。「残りものを買う」というネガ感情を払拭し、店舗あたり5個の売上増につながったという。
日本文化の中で磨き抜かれてきた「漫画的な記号」はコミュニケーションスピードが速く、商品ひしめくコンビニの棚でも一目で意味伝達ができる。ファミマの涙目シールはこの記号のパワーを活用し、店頭で「廃棄寸前のおにぎりと目が合ってしまう」という体験創出に成功している。

画像出典:値引き品は恥ずかしい? 「涙目シール」で心理的抵抗を克服、ファミリーマート
事例③:人気マンガのパパ3人が、父のホンネを代弁
「ユーザーの代弁をする」ことで、広告は人に寄り添える。ユニクロの父の日広告はバカボンのパパやヒロシがちゃぶ台でビール片手に「父の日忘れられたらツラいから忘れちゃおう!」などと語り合う。「1日の『ありがとう』で、364日がんばれちゃう。」のコピーも、ユニクロのLife Wearとの親和性も秀逸。
国民的な漫画の「パパ」同士を異世界コラボさせ、いじらしい会話を繰り広げる展開は「くすぐり要素」満載だ。パパ本人が言いにくいことを、バカボンのパパやヒロシがチャーミングに代弁することで日本に蔓延する「父の日忘れられがち問題」の課題解決にもなっている。

画像出典:3人の国民的マンガの「父」が語り合う、ユニクロの父の日広告
▼この内容はポッドキャストでも配信しています▼
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…
99%が無視される過酷な情報環境下で、有効な広告のフックのひとつが「異物感」だ。コンテクストの一部に裏切りを仕組むことで思わず二度見させ、ブランド記憶につながる関与を生むアプローチ。広告に異物感を仕込むことは、表現としての差別化を図[…]
国民食やロングセラーのお菓子など、日常にすっかり溶け込んでしまったおなじみ商材の魅力を改めて喚起するには「物性シズル」を別のアングルから捉えなおさせることも有効。商品の物性ど真ん中を新鮮な角度で見せることで妙に気持ちが掻き立てられ「ひさびさ[…]
「朝専用」など利用シーンを限定することで商品のエッジが立ち、存在感が立ち上がる。茫洋たるマーケットの中で普段は埋もれていても、特定の時間帯と紐づけておくことで定期的に想起されるブランドになれる。今の生活者は賢いのでシーンを限定したからといっ[…]