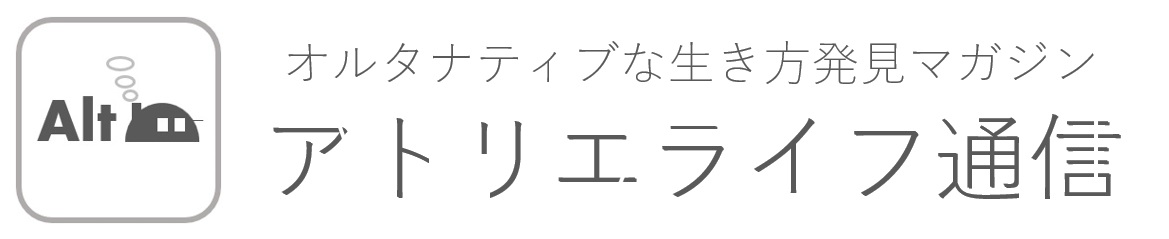「この長い物語も、おわろうとしている。人は死ぬ。竜馬も死ななければならない。その死の原因がなんであったかは、この小説の主題とはなんのかかわりもない。」
司馬遼太郎「竜馬がゆく」最終話の一節だ。久しぶりに全8巻を再読し、英雄の人生に想いを馳せていた矢先の報せだった。長嶋茂雄が、この世を去った。
竜馬(坂本龍馬)と長嶋茂雄。日本人の「英雄観」に最も影響を与えた2人といっていい。長嶋茂雄がプロ野球デビューしたのは終戦から13年後の1958年。焼け野原から戦後復興を重ね、高度経済成長期へと飛揚するこの時にデビューした長嶋は、いきなり3割29本37盗塁をマーク。ベース踏み忘れの1本がなければルーキーイヤーでトリプルスリー達成という「らしいエピソード」のオマケつきだ。
竜馬がゆくの新聞連載はこの4年後、1962年に始まっている。小説の構想を練っていた時期は、長嶋茂雄の鮮烈なデビューから国民的ヒーローに駆け上がっていく時期と重なる。竜馬の「英雄像」に長嶋の影響がなかったとは思えない。
私たちの「英雄像」を考えること。それは、一人ひとりがこの世に生まれてきた理由を定義する「夢」や「目標」を定める上での「太陽」の位置を理解することに他ならない。私たちはどのような太陽をいただき、どんな熱量をもらっているのか。それを明らかにしたい。
日本人が愛する「英雄像」
小説の竜馬は無愛想ながら会う人を一瞬で虜にする人間的な魅力を持ち、勝海舟をはじめ松平春嶽、薩長の重臣、そして最終的には土佐の上士階級である後藤象二郎・乾退助までを引き入れてしまう。この魅力の根源には些事に囚われない「大らかさ」とそこから生まれる「大局観」があるだろう。
長嶋茂雄もまさにそうだ。バットも何でもいいし、バッティングフォームも臨機応変。自分がカッコよくさばける球は誰の球でもさばくし(ファーストゴロも3回さばいたらしい)、逆に画にならないフライはそれがサードフライであっても「クロちゃんたのむ」で済ませてしまう。
真っすぐさと要領のよさを併せ持ち、ズルしてもどこか憎めない天衣無縫の男。そしてここぞという時には必ずキメてくれる勝負強さと、「ここぞという時」が不思議とよく回ってくる運の巡りを持っている。長嶋が日本で初めての天覧試合でサヨナラホームランを放ったことや、松井秀喜をドラフトで引き当てたことは有名だが、テレビ特番のプロ野球じゃんけん大会でも鬼神の如き強さを発揮し、ちゃっかり優勝している。
天覧試合のホームランはあまりにも有名な話ではあるが、本当の凄さは端折られて正しく理解されていない。入団二年目に行われた天覧試合では、まずその後106回続く「長嶋・王のアベックホームラン」の第一号が生まれている。そして、長嶋が有名なサヨナラホームランを放ったのは、その後だ。陛下の帰宅時間が過ぎてもまだ勝敗がつかない・・その時に決めた「2本目のホームラン」なのだ。この瞬間、天皇家に永らく受け継がれてきた「カリスマ」が、民間に継承された。長嶋茂雄という「ミスター」の称号を冠する男に。そしてそれは、新聞タテ一面の「画」によって、日本国民に告示されたのだ。
システム1で生き抜いた男
現役時代の長嶋茂雄は、まさに「天馬空をゆく」自由自在のプレーをみせた。躍るようなフィールディングは、歌舞伎の動きを取り入れたというが、テレビ時代のスーパースターたる所以だ。この頃は関東はもちろん関西も巨人、というか長嶋を応援した。日本人を惹きつけてやまない理由の一つに、「野性的勘」と評された直感の鋭さがあるだろう。
ノーベル経済学賞をとった「ファスト&スロー」のダニエル・カーネマン的にいえば、長嶋茂雄は40歳まで「システム1」(直感・本能・95%の無意識領域)主導で生きた男だ。これはほとんどの日本人には容易ではない。社会の目を気にするうちに「システム2」(理性・規律・5%の顕在意識領域)偏重になり、躍動感はなくなりどんどん小さな檻に収められてしまう。
アスリートとは、ルールに基づいて捨象された競技空間の中で、我々一般人に人間の根源的な力や強さの引き出し方をわかりやすく見せてくれる存在だ。長嶋茂雄はブラウン管を通して全国の日本人に「システム1で生きること」を体現し、勇気を与えた。誰だって本当はシステム1主導の「無敵モード」で生きたい。だからこそ、そのお手本を生き生きと見せてくれる人に魅力を感じずにはいられないのだ。
若いころから天賦の才を発揮してきた男性は、40歳頃に新たな役割を担うことになり「システム2」に目覚めだすと途端に「面白オジサン化」する傾向がある。監督となった長嶋もそうだし、安全地帯からソロ活動を本格化した玉置浩二もそうだ。溢れんばかりのなサービス精神と大胆な枠組みの発想、その一方で「配慮しなければならないあれこれ」との綱引きで「ほつれ」が出てしまう。それがまた、たまらないのだが。
「基準」の違いが、英雄を生む。
様々な球団に、そして他の様々な企業や団体にも「スター」は存在する。だが「スーパースター(=英雄)」との違いは何か?長嶋茂雄は、明確な答えを示している。「みんなの期待に応えていくのがスター。みんなの期待を遥かに超えていくのがスーパースターだ。」長嶋がその他すべての日本人と根本的に違ったのは、このGOAL基準の違いだ。普通のスターは感動を作るが、スーパースターは「新しい感動の味」それ自体を創り上げていくのだ。
たとえば長嶋がプロ野球に入った1958年当時、実はプロ野球は人気がなくて、大学野球全盛の時代だった。「野球をして金を稼ぐなどけしからん」というシステム2的なムード・常識が邪魔をして職業野球は日陰の存在だったのだ。それを六大学のスター長嶋が変えた。そして王が続き、伝説のV9を達成し、いまやプロ野球は日本最大のスポーツ興行だ。
長嶋茂雄の魂は、いうまでもなく大谷翔平に受け継がれている。大谷は野球の本場、メジャーリーグにおいて「全く新しい感動の味」を創りあげている。エンゼルスのエースを張りながらメジャーのホームラン王になる「二刀流」の夢。そして2023年のWBC日本代表の優勝や、2024年のドジャースワールドシリーズ優勝(コロナ禍で微妙な20年を除けば、1988年以来となる36年ぶりの快挙)など、長嶋茂雄の魂を受け継ぐスーパースターとして「新しい感動の味」それ自体を創造し続けている。
▼この記事の内容はポッドキャストでも配信しています▼
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…
終戦から14年後の1959年6月25日、後楽園球場で初のプロ野球天覧試合が開催された。3-3の同点で迎えた9回ウラ、阪神のマウンドにはこの年沢村賞を受賞した新人の村山実。試合を決めたのは、カウント2-2からの長嶋茂雄の一振りだった。翌日の新[…]
長嶋茂雄がプロ野球界、いや国民的スーパースターになるまでの日本では「野球なんぞで給料をもらうなんてけしからん」と考える人が多かったという。今ではそんな人は少なくなったとはいえ、スポーツの社会的役割や本来の価値が正しく認識共有されていると[…]
聖書というのは割と正直で、時の教皇によって何度か改ざんが加えられているものの、イエスの人間的な弱さや迷いも隠すことなく記されている。それが逆にイエスの実在性を信じる拠りどころにもなっていたりするのだろう。たとえばゴルゴダの丘で十字架[…]
仕事ができる人とは、何だろうか?私は広告代理店やメディアという立場で、様々な企業に出入りし、数えきれないビジネスパーソンとお仕事を共にしてきた。素敵な人もいたし、カッコいい人もいたし、尊敬する人もいたし、もちろん二度と顔をみたくない人もいる[…]
言葉というのは時に幻想を日常化させる。たとえば「モチベーション」という言葉が一般化すると、うまくいかない理由を「モチベーション不足」に帰属させて安心したくなるが、そんなものは幻想。行動が引き出されないのは内的要因ではなく、目標の欠落[…]
学生時代からやりたいことは文字で描写し、しばらくは繰り返し読むという習慣があった。文字で書くと夢がどんどん弾むのだが、そもそも当たり前のことは夢とは呼ばないのでそれでよいのだ。「思考は現実化する」なんて陳腐なことを言うつもりはないが[…]