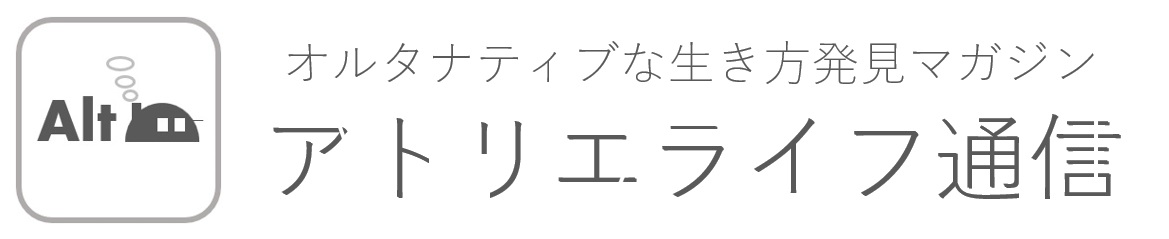先日社内会議でしゃべっている中でふと思い出した昔のコトをTwitter(現X)でつぶやいたら、広告業界(現出版社経営)の大御所・田中ひろのぶさん(まあ説明は不要でしょう)に強く共感いただき、「結構芯を食った発見だったのかも」と思ったので改めて考察を深めてみたい。
たぶんひろのぶさんも今年から宣伝会議のライティング講座を受け持ち、その中で「受講生になんか伝わらんな~」と感じるポイントなのかもしれない。一言でいえば「What to Say?」なのだが、企画の骨子を「一点」に定めるコンセプト的な意味合いではなくて、文章を綴るときの「何を綴るか」という話。
ここがズレていると、書けば書くほど記事はとんでもない方向にズレていく。そして書き散らかした割には読んでも読んでも何も脳裏にイメージが立ち上がってこない、という状態になる(世の中のほとんどのWebテキストがそれだ)。
「文章を作るための文章」禁止令。
ライターと一緒に取材してあがってきた原稿みるとなんで巷の文章がぜんぶダメダメなのかわかる。文章を文章としてまとめるために使えそうな要素(概ね一般論)だけを抜き出して、本来の目的である「読者の態度変容」に使えるナマモノ言葉は取り扱いが難しいから捨てられている。これがご馳走なのに・・
先日も事例記事のテコ入れプロジェクトに関わったのだが、いずれの記事も「読んでも読んでもイメージが立ち上がってこない」ものばかり。取材音源はあったのでためしに記事と比較してみると、やはり悉く「目的=態度変容のために盛り込む要素」は無視され、文章をつないでまとめやすくする要素だけで書かれていた。これではどれだけテキストを並べても「・・しかしなにもおこらなかった」となるのは当然。
その記事ならではの「味わい」を構成する材料選定
広告も記事も、まずはWhat to Say?がすべて。取材記事の場合は、話者のトークの中からどの情報要素をチョイスするか?がすべて。扱いにくいナマモノ言葉こそ、その取材記事ならではの味わいを持つ要素であり、それを軸に組み立てるべき。それには抽象的な処理が必要になるが、それこそが編集・ライターの介在価値であり、それがなければ付加価値どころか逆に10の内容を3や4に解像度を落として伝えているだけ。
では、選定すべき材料とは何か?いくつか例を挙げてみよう。
素材①:「一歩目のCVポイントの境目」で背中を押す描写
「餌となるFE情報だけでは全然足りなくて、やはりもう一歩踏み込んで「体験」してみないとダメだと思った」というような顧客の「望ましい判断」を、顧客自身の言葉で言ってもらうことで、今後の見込み顧客から同じ行動を引き出せる。
素材②:「体験価値の実感」をイキイキと描写した表現
ファン化するにはプロセスがあるため、既にファンになった人からそのプロセスをイキイキと語ってもらうことで、読み手の追体験を創出。化粧品なら「人に会いにいきたくなった」という初期の感動があり、使っていくうちに肌質改善があれば「毎日起きるのが楽しみになった」というような感動体験プロセスがある。
素材③:期待していた価値以外の「副産物」の発見の嬉しさ
メインのベネフィット以外にも、ユーザーごとに発見するサブベネフィットがある。その人なりの立場や視点で見たときのサブベネフィットを切り出して見せることで、購入理由が倍増するし、自分ならではのサブベネフィットを見つけたくなる。
素材④:利用開始後のユーザーの「景色」を見せる
ナーチャリングコンテンツの基本は、未利用者に利用者の「景色」を垣間見せること。利用前には狭くて陰鬱だった視界が拓け、今の毎日はどれほどまばゆいものであるか。イケてるSaaSツールであれば「月曜日が待ち遠しい」「夜お酒飲みながらもずっと触ってる」といった実感の声があれば最強。
素材⑤:新たな「夢」の発見
ベネフィットの享受によってひとつ壁を乗り越えたユーザーは、視点がひとつ上がるため、新たな「やりたいこと」が出てくる。その人の立場なりの具体的な新たな夢が何かを見せることで、逆説的にそのサービスのベネフィットが浮き彫りになる。
AI時代のライターに必要なこと
生の言葉をいかにいらんことせず(そのために寿司職人ばりに裏でメッチャ色々とやるわけだが)出すかが全てで、「文章を整えるための文章」をくどくどと並べるのは悪いクセだ(それAIでもできる)。特にSEOに毒されたWebライティングギョーカイは、クセ強すぎてもはや抜けない感がある。
既に@ 1円ライターレベルの文章だとAIで充分に書けてしまう。AIがあげてきた「一見メッチャええ感じやん!」って文章を、数秒後「・・いや、よーみたらぜんぜんあかんやん!」とベキベキに解体するのがニンゲンがやるべき「編集」だ。「っぽい文章」のダメさを見抜けないのが第一関門。
「っぽい」お作法って、ある日突然コメディ化するので、公式なテキストで書くのは”逆に狙っている”場合以外はかなりアブナイ。ツイッター(断固 Xとは呼ばない)でも「断言します」とか「何度も言いますが」とかで語りはじめるヤツらにはトランプから追加関税かけられろと思う。
たとえば10年前にコメディ化してる、記事の締めくくりの見出し「いかがでしたか?」を最近も使ってる記事あるが、あれは完全に「吉本新喜劇の世界」である。いまだにリアルガチで書いてる人いるが、逆にインタビューしたいくらいである。
編集者とコピーライター。同じメディア制作という領域にいながら、実はあまり交わることのない両者。書くことでメシを食っていき…
前回記事『なぜWebメディアのテキストは読まれないのか?ヒトに向けて書かれていない「Webライティング」問題を構造的に考える』では、現状のWebライティングがそもそもノウハウとして構造的欠陥があるという点を指摘し、巷のメソッドは一度アタマか[…]
広告やメディアに限らず、WantedlyやNoteなどの採用広報・採用マーケにおいても情報化が進み、ビジネスのあらゆる領域でテキストコミュニケーションの重要性が高まっている。一方で、プロでない人が書いているので皆が他社を見よう見真似で書いて[…]