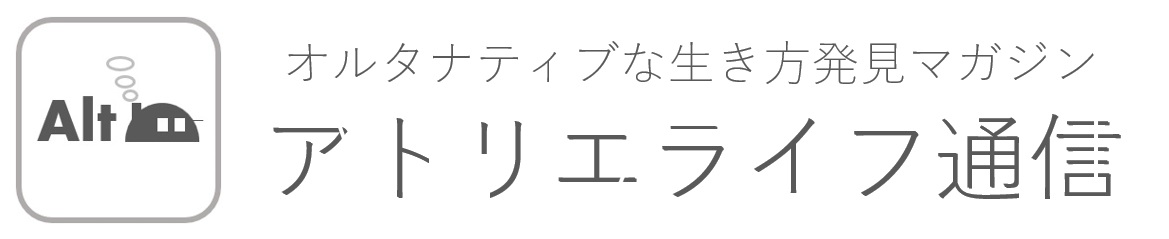AIで「っぽい」ものが簡単に作れるようになると、これまでモノを考えなかった人がもっと考えなくなる。逆にAIを従えて自分自身の脳を無限に賢くする人も現れるので、その差がエグいことになる。大事なのは納品じゃなくて、納品に至る体験と情報を通して脳を鍛え続けること。思考は外部化しちゃいかん。
しっかりと考え抜いた仕事は、当然記憶に明瞭に残っていく。振り返ってみたときに、それらが自分の思考プロセスのマイルストーンになる。自分の思考の「型」が確立されてくれば、好不調の波に左右されることなくどんな案件でも自分らしい解き方でアウトプットを導けるようになる。
いつの時代も【自分という「絶対値」 × 時代という「変数」】という公式は変わらない。となれば、予測できない変数ではなく、毎日の積み重ねの成果物としての「自分」という絶対値を絶対化していくことの方が実りある選択ではないか。
「っぽい」もので満足しない仕事術
ベンチマークしすぎると思考停止する
他社のやってることを横目でベンチマークするのは必要だが、そこから「学ぼう」とか「真似しよう」とか思ったら駄目。だいたいどこも隣同士をモノマネし合ってるので見渡す限り「ぜんぶ間違い」だと認識すべき。ゼロベースでそれらと次元がひとつ違うことをやらなきゃ勝てないし、そもそもつまらない。
あまり真剣に見すぎると、どんどん視野が狭くなるのでベンチマークは「横目」で見るくらいに留めておくにかぎる。競合のオウンドメディアも林立しているし、コンテンツは無限にある。ただ現実問題として競合の担当者でもコンテンツの文章単位までいちいちすべて認識しているわけでもないので、企画単位や切り口単位で俯瞰的に見るくらいに留めておくほうがよい。
そもそも存在感のあるオウンドメディアだからといって戦略や内容が素晴らしいとは限らない。単にそもそもの企業がメジャーだったり、プロダクトのユーザー数が多い結果としてオウンドメディアも注目されるということがよくある。原因と結果をはき違えてそれを真似したところで、自社が同じようにうまくいくことはない。
「まだ見ぬすごいもの」を立ち上げるには、まずプロトタイプを作ること
他社の仕事をトレースするようなことは自分の仕事じゃないと思っているので、あらゆる案件がゼロイチになる。それは仲間はもちろん自分自身もまだ見たことないので、プロトタイプを作る必要がある。これが同時多発するとクタクタになるが、これこそ仕事の醍醐味である。
たとえば同じプレスリリースでも、切り口や構成、語り口はゼロから組み立てる。プレスリリースの場合リード文は工夫の余地がほぼないので、本文にいかに気づきを濃縮するかがポイントになる。その上で、締め部分に深い洞察を与えるコラムを入れて企業情報に接続する。広報界隈がキョロ見して真似っこしているものを同じようにキョロ見しても何も起こらないので、最低限のルールを押さえた上で(この確認のために他社リリースは見る)最大限の飛距離を狙う。
これしかない「解」をつかみ取るまで、思考やデータの海に「潜る」
同じ納品するでも予定調和で納品しはじめたら成長しなくなると思う。昨日までのすべてのチャレンジを土台にして、まだ見たことのないアウトプットを作りにいく。コピーも記事1本も変わらない。ゼロベースで取り組むと毎度答えが見えず彷徨うが、必ず掴みとってくる確信を持ってデータや思考に潜る。
企画の「軸」は誰かが決め切らないと、いつまでもフワフワしたまま(多くの場合はそのまま納品される)。だから誰かが責任を持って「引き受け」て、答えを出しきらないと前に進まない。納品してお金もらえたからオッケー、なわけがない。
思考のフレームワークは型を知ることには何の意味もない。それを実務を通して角が丸くなるまで使い込み、カラダに馴染ませる10年単位のプロセスの集積こそが人的資本価値。広告だと意識せずとも複数の型を通したアイデアの鋳型がパッと出てくる状態。結果物もそうだが、着眼点、思考全ての精度が上がる
人は往々にして過去問や他社事例を安易にパッチワークしてインスタントな解を出そうとしがち。しかしこと広告・マーケティングにおいては、競合の施策を参考にするのはご法度。そもそも差別化をするためのマーケ活動において真似をするなど自己矛盾も甚だしい[…]
なぜ日本のタイアップは「片想い」なのか。代理店時代、メディアに記事広告を依頼することが多かったが期待してあがってきたら「超薄味」てか、無味無臭。広告主のメディア愛を受けてのタイアップなのに、メディアサイドは塩対応。この歪んだ関係性、どう[…]
マーケ現場の「なんか違う」は、一歩目の踏み出しの弱さ=言語的整理の不足が原因。まずはコトバで太い骨格を通した上で(STEP①)、デザインによってそれを肉付けする(STEP②)のが基本だが「それっぽいが何も言ってない未完成なコトバ」をベースに[…]
▼この記事の内容はポッドキャストでも配信しています▼
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…