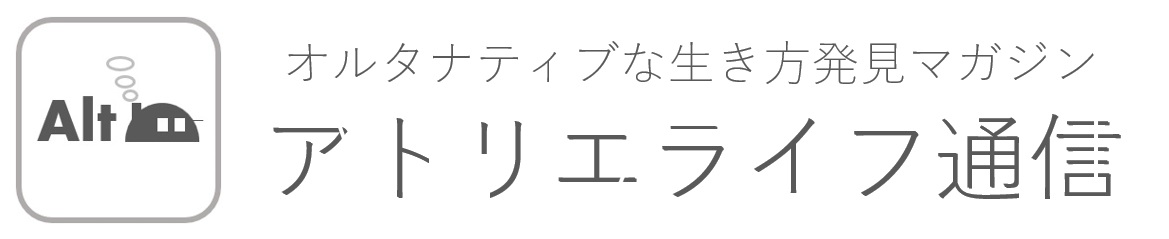社員同士が「価値観」でつながる時代、企業のインナーコミュニケーションの重要性は増しており、MVV策定はもちろん社内報や社内ポッドキャストなども活発になっている。ただ何より鋭利にトップの意志伝達を可能にするのはそれに紐づく新たな「ルール」を提示すること。これでホンキ度が一発で伝わる。
企業の未来に向けての新しい取り組みが生まれたら、その兆候を顕在化するために〇〇制度や〇〇プロジェクトなどの「名前」を付けるべき。名前が付くと社内に流通しやすくなるため、速やかな価値観の合意形成が生まれる。同時に浸透しやすいキャッチーな名づけは、採用や広報など社外への発信にも好都合。
以前とある企業の採用コンテンツを制作した際、無償で他社の業務を手伝って経験と人脈を築く取り組みをしていたので、その取り組みに「武者修行制度」というネーミングを付けることから提案した。キャッチーなコンセプトを軸にするとコミュニケーションスピードが速く、結果反響にもつながりやすい。
経営の意志は、評価制度や社内システムなどとセットになっていないと単なる「お題目」になる。会社というのは最終的に評価して報酬を払う場所なので、そこから外れた行動はボランティアとなり動員は難しい。イケてない社内システムの放置は「イケてない仕事のままでいいんだよ」というメッセージになる。
ルールという名の表現手法で企業の「意志」を伝える
事例①:BAR経験者を優遇するハイネケンの採用基準
会社を構成するのは「人」なので、どんな会社であるか(orになるか)を端的に社会に示すには入口の「採用基準」が有効。各社が「コミュ力」「創造性」など軒並み似たような求める人材像を掲げる中で、たとえば没頭力を表す「オタク度」などを提示すれば企業の意志とニーズが鮮烈に打ち立てられる。
社会課題への取り組みは有意義だが、まずは自社ビジネス周辺から着手すべき。ハイネケンは BtoBの最重要取引先のBARの人材不足解消のため、就職人気の高い自社の採用基準に「BAR EXPERIENCE」を追加。またマネジメント層のバー経験も公開するなど、経営の根幹から社会課題にコミットする姿勢を見せた。
ハイネケンにとってはその一番の体験スポットであるBARカルチャーの温存を図ることは、ビジネスの土壌整備をすることにつながる。またそのカルチャーを深く理解する人材を優先して採用することは、これからの新たなブランド価値展開を推進する上で欠かせない視点を会社の現場にもたらしてくれる。
事例②:マイナビバイトの「座ってイイッスPROJECT」
企業姿勢はキレイゴトをいうより、具体的な仕組みで提示すべき。たとえば従業員を大事にする姿勢を見せることで、お客様はもっと大事にされるだろうと感じさせられる。マイナビバイトが仕掛けた、レジに小さなパイプ椅子を置く「座ってイイッスPROJECT」もその一つ。何となく立つのが当然・・という社会意識を打破し、働く人の無駄な負担を軽減した。
座って接客してもいいと思う雇用主は73%なのに対し実際に座って接客しているのは23%。客は8割が気にならないとしているが「なんとなく」多い立ち接客。マイナビバイトはそれを変えるために店舗への呼びかけだけでなく、実際に日本の狭いレジスペースでも置きやすく座る&支えるができるハイチェアを開発した。
事例③:職場を「夢を叶える人が働く場」と再定義したモスバーガー
人手不足を打開しようと思ったら、求人広告で「謳う」のではなく、制度や取り組みで解決する方法もある。モスはアルバイトスタッフの中から次世代アーティストを発掘して支援するMOS RECORDSを開催。「働く場所から夢を叶える場所へ」の転換を図り、エンゲージメント増加と共に求人応募も20%増加した。
MOS RECORDSを開催したモスバーガーは下働きであるアルバイトの職場を「夢を叶える場所」と再定義することで、「ここで働きたい!」という気持ちを喚起している。アーティストは一つの象徴だが、他のメンバーもそれぞれが「夢のための下準備」という文脈の中で働けるので肯定感が高まる。
▼この内容はポッドキャストでも配信しています▼
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…
リモートの定着と、SlackやZoomなど便利なコミュニケーションツールの整備によって「職場」という概念が更新されつつある。オフィス勤務していても、社内すべてのやりとりが「見える化」されるSlackなどの心理的な影響は大きく、社内チャット空[…]
瞬時の接触でメッセージを伝える広告において大事なのが「コミュニケーションスピード」。そのために必要なのが、考える前に「意味がほどけるようにわかる」設計。でも最初から意味がほどけてたらダメで、アタマの中で意味をほどいていく「過程」が認識的体験[…]
「朝専用」など利用シーンを限定することで商品のエッジが立ち、存在感が立ち上がる。茫洋たるマーケットの中で普段は埋もれていても、特定の時間帯と紐づけておくことで定期的に想起されるブランドになれる。今の生活者は賢いのでシーンを限定したからといっ[…]