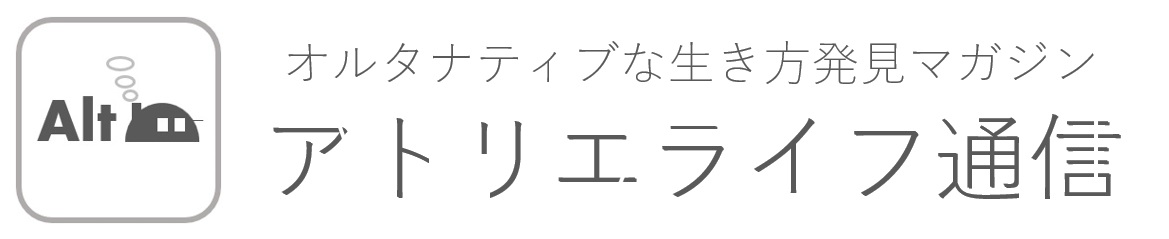生成AIの登場に加え、検索結果のAI化も進みSEOのトラフィックは雲行きが怪しい。これまでは(クエリに対する)顕在ユーザー吸引器だったオウンドメディアも、役割のアップデートが必要になる。闇雲なSEO記事量産ではなく、金を払って誘導してでも読ませる価値のあるコンテンツを置くことが重要になる。
オウンドメディアは格納するコンテンツによってブランドの世界観を拡張&濃縮する装置。そのブランドの物性や体験価値を様々なアングルから再解釈し、新たな意義づけを加えていく。ブランドのファンにとっては映画館のパンフのようにナラティブのネタ帳でもある。SEO的なコンテンツは「隠す収納」行きだ
ナラティブのネタ帳としての「オウンドメディア」戦略
事例①:ヤマハの「HATSUDO」
10-20代の約半数がオートバイメーカーを想起できない。ヤマハは24年にオウンドメディア「HATSUDO」を開始し、長期的な関係性構築に着手する。乗り物を作る会社として、外に出ると素敵な発見があり、新しい自分に出会えることを訴求。製品を押すと若者の価値観からは離れるので製品登場は1コーナーのみ
事例②:丸亀製麺の「もちもち きもち 研究所」
Pick UP⑤:食感シズルを掻き立てる情報クリエイティブ
食感シズルは擬音語や動画だけでなく、情報クリエイティブでのアプローチもある。「うどーなつ」が好評の丸亀製麺は「もちもち きもち 研究所」で弾力感と包み込む優しさを持つ「もちもち食感」の可能性を探求する。脳波を計測した第一弾の実験では集中度が約20%向上し、ストレス軽減効果も認められた
「もちもち きもち 研究所」は専門家に依頼した独自の研究結果をオウンドメディアに載せているところが秀逸。独自性も専門性も担保されており、実験素材としてうどーなつの物性紹介も自然な形で詳細に行っている。ただ、1コンテンツあたりの制作にかなりの手間ヒマがかかると見られ、まだ1記事のみ。
事例③:カンデミーナの「RPG」体験訴求
商品の物性にエッジを立てるためには様々なアプローチがあるが、Web上のRPGゲームで表現するのは没入感が高い。カンロのカンデミーナはそのハードな食感を訴求するため「ストレスフルRPG 魔王ムキーの挑戦状」を制作。ストレスを感じすぎてゲームオーバーするたびにカンデミーナで復活する
カンデミーナRPGの世界観はドラクエを踏襲。最強だがストレス耐性がない勇者が「王様の話が長すぎる」「究極の呪文が長すぎて覚えられない」「タンスを開けたら怒られる」など、ドラクエ文脈を下敷きにした裏切りイベントによる21のストレスイベントをグミの歯ごたえで乗り越えていく。
以前にも指摘したように、現在のWebメディアはSEO的な集客のためのコンテンツに終始しており、集めたユーザーをどうしたいかという視点が欠けている。KPIを達成することに縛られて、本来の目的を見失っていることがその要因だろう。目標のUUやP[…]
前回記事において、今後のオウンドメディアはナラティブの起点となるべきであるという話をした。それを受けて今回は、具体的にどのようなコンテンツによってどんな心理作用を生んでいくのかを考えてみたい。私たちが「態度変容」する瞬間あらゆる広告コミュ[…]
旅先へ行くと、日常では考えもつかなかったような視点が得られることが多い。私はそのために旅に行くといっても過言ではない。その要因のひとつには「日常からの離陸」もあるだろう。今はそうでもないが、10年ほど前までは旅先では名実ともにオフラインにな[…]
▼この記事の内容はポッドキャストでも配信しています▼
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…