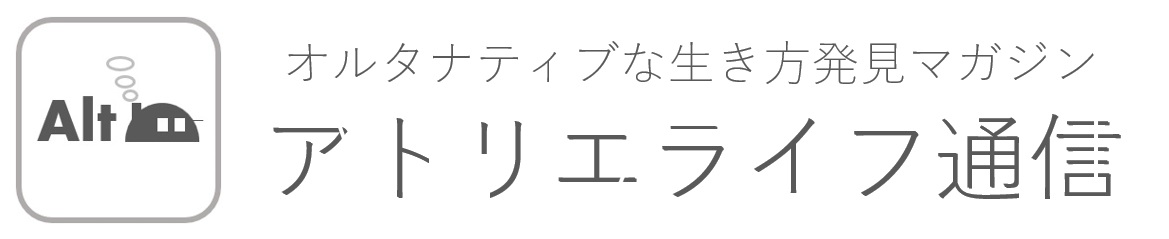空間ジャックやラッピングなど、大胆な枠づかいで街中に体験接点をつくれるOOHは「どこでも展示会場」ともいえる。展示会はわざわざ顧客に来てもらわねばならないが、OOHで出展すればこちらから生活者の方に出向いていけるので会場集客コストも会場設営費も節約でき、その分さらに枠を買い増しできる。
誰かが注目していると人は気になるものだが、OOHによる「どこでも展示会」は多くの人が足を止め、スマホで撮影をする様子を周囲の大勢の人波が観る構図が生まれる。結果、多くの人の「気になる」を生み、SNSやナラティブでも拡散され、「今日のトピック」に登り詰める。これぞ世の中ゴトメディアだ。
人混みの真ん中で「どこでも展示会」を開催
事例①:枠取りを表現キャンバスにしたハウスメイト
OOHは掲出場所のカタチや枠取り自体が表現のキャンバスになる。地下鉄の通路の左右に電飾枠が続く新宿アドストリートを活用したのが「ふしめ、ふしめにハウスメイト」のキャンペーン。オンエア前にCMの画コンテを掲出し、1月からの新CMの期待感を醸成した。歩行者は歩きながらひとコマずつ読める仕掛け。
CDの玉山貴康氏は新宿アドストリートを見たときゲームの地下通路のような異空間性を感じたという。そこで、展覧会のように1コマずつ画コンテを並べることで身体性を伴う広告接触体験を創出できると考えた。面のインパクトに安住せず、画コンテという普段は露出しない下書き部分の異物感を加えて強化。
事例②:OOHの「額縁性」を活用したマッキー35周年広告
OOH(屋外広告)は多くの場合「額縁」に掲出されるので、アート作品のように手描きの一点モノを掲出することでリアルな存在感を作れる。槇原敬之デビュー35周年に掲出されたのは「マッキーをマッキーで描くOOH」で渋谷と大阪のビッグボード枠2箇所に別デザインで掲出されQRコードまで手描きで描かれた
基本的にはマスコミュニケーション施策であるOOHのポスターだが、あえて「手描き」にすることで強烈な異物感と臨場感を演出できる。槇原敬之35周年ポスターはマッキーをマッキーで描く、というギミックも手伝って思わず撮ってインスタに上げたくなる、誰かと話題にしたくなる設計が巧妙だ。
事例③:雪印コーヒーの「受け流せないポスター展」
ロングセラーは認知率や体験率も高いが直近の購買は減少することも多い。60年超えの雪印コーヒーは受け流しのプロ=ムーディー勝山を起用して過去のファン向けのCMを制作。漠然と疲れている人々に対し「甘さで全てを受け流せ」と促す。また原宿や品川のOOHスペースで「受け流せないポスター展」を展開。
共感を得るために広告では「あるある」が使われるが現代人はあまりに疲れすぎているため「疲れあるある」は疲れを追体験させてしまう。そこでコーヒィ勝山が疲れた世の中をチャーミングに見せてくれるクリエイティブを展開。キマりすぎたために通常の広告掲出に加え展示会的な見せ方も実施したという。
多様化するメディアだが、今メインのコミュニケーション経路に絞るとざっくり「スクリーンのあっち側/こっち側」に2分割できる。テレビ、スマホ、PCなど分厚い前者に対して、後者を担うのは基本的にOOH(=Out of Home/屋外広告)。あっち[…]
「広く告知する」ことが使命の広告において「あえて潜伏する」「待ち伏せする」ことでメッセージ強度を高められるのはOOH(屋外広告)ならではの醍醐味。ゲリラ戦のように街のあちこちで待ち伏せし、意外なポイントで突如姿を現してメッセージ伝達すること[…]
エンタメを中心に「新種の体験価値」が生まれ、生活者の感度も養われている中、ブランドも体験型のコミュニケーションが活性化している。最も手軽なのはOOHのメディア掲出だが、最近はポップアップ型の体験場や展示会も増えている。会場という世界観がある[…]
▼この記事の内容はポッドキャストでも配信しています▼
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…