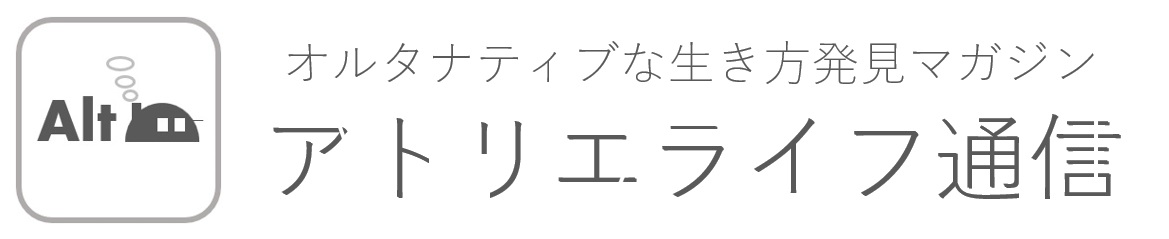エンタメを中心に「新種の体験価値」が生まれ、生活者の感度も養われている中、ブランドも体験型のコミュニケーションが活性化している。最も手軽なのはOOHのメディア掲出だが、最近はポップアップ型の体験場や展示会も増えている。会場という世界観があることでエッジの効いた体験価値提供ができ、一度で忘れられない体験記憶が生まれる。
体験型の企画は、全身でブランド体験する強度の強さはもちろん、その体験自体の味わいは千差万別なので圧倒的差別化も図れる。ディズニーのコースターでブン回された体験記憶をUSJと取り違えることはないように。リーチこそ限られるが、一度巻き込まれた人は生涯そのブランド体験記憶と共に生きてゆく。
体験価値の時代に最適な「箱型アプローチ」の実例
事例①:なにげないSNS投稿と表裏一体の他者の「悪意」を体験させる
生活者の価値観が体験重視にシフトする中、ブランドの臨場感を上げるために体験型の展示会を開催する企業が増えている。NTTドコモの「ばくモレ展」は一見うまく盛れているように見えて、実は瞳に映った景色やピースサインの指紋から個人情報が漏れていることを気づかせるショック体験を促す展示会。
ばくモレ展は日常の楽しいSNS投稿の裏で待ち構える他者の「悪意」を、表裏一体のものとして体験させることでリスク観のショッキングな捉えなおしを促している。「あの日以来行動を改めた」というきっかけは絶対に忘れることはないし、結果的にドコモユーザーのトラブルの少ないスマホライフにつながる。
事例②:日常のネガなモーメントをブランド利用のキューサインにする
ブランドの利用頻度を上げるには、利用チャンスを啓蒙しておくのが有効。ミンティアは代官山T-SITEで「日常のなんてこった書店」を開催。TBSラジオでネタを募集し「さっき結んだ靴紐がまた解ける」「カフェWi-Fiのパスワードがやたらと長い…」などの時にミンティアでリフレッシュすることを啓蒙。
日常のなんてこった展はリフレッシュすべきちょっとネガな瞬間を「なんてこった」というチャーミングなアングルから切り出して、そこにすかさずミンティアを紐づけるアプローチ。「なんてこった」な瞬間は生きていれば度々あるので、そのモーメントをまるごと利用チャンスに変えてしまおうという試み。
事例③:都市伝説化した「京都のいけず」を体験させる
よく聞くけど体験したことはない、という地方あるあるは都市伝説化して強度が高い。京都特有の物言いもそのひとつで「この先いけずな京町家」はそれを体験できるイベント。おかみから放たれる「いけず」に気づいて適切な対応がとれなければ、ぶぶ漬けを出されてゲームオーバーというシビれるゲーム設定。
食や名勝はその場にいけば体験できるが、人の振る舞いは難しい(関西人のボケツッコミ以外は)。「この先いけずな京町家」はもはや都市伝説化している京都のいけずなコミュニケーションを体験型テーマパークとして提供することで「よく知ってるけど見たことない」という欠落を埋めるアプローチ。
事例④:少年時代にタイムスリップ
体験型アプローチを強化するギミックのひとつがタイムスリップ。サントリー「あの夏休み自販機」は民家前の自販機のボタンを押すと中から友だちのママが登場し、04年の部屋に招き入れてくれる。なっちゃんやC.C.レモンでもてなされながら友だちの部屋に隠されたある秘密の謎解きに突入していく仕掛け。
謎解き×タイムスリップというギミックの二重奏で構成されたサントリー「あの夏休み自販機」。だが20年前=30歳の人が小4で遊びに行った友達の部屋を再現することでさらにそこに「ノスタルジア」も加味している。タイパ重視で「失敗したくない」現代人にとっても二重三重の体験価値設計は安心材料になる。
▼この内容はポッドキャストでも配信しています▼
ポッドキャストのエピソード · あした使える"聴く"ネタ帳 | マーケターの真夜中ラジオ| マーケティング · 2025…
戦後~70年代あたりまで、まだモノが希少だった頃は機能価値をそのまま訴求すれば売れた。やがてモノが飽和してくると、広告の売り文句によって差別化を図る必要性が生まれ、気づきや驚きを促すコピー表現技術が発達した(ex.不思議、大好き。:1981[…]
多様化するメディアだが、今メインのコミュニケーション経路に絞るとざっくり「スクリーンのあっち側/こっち側」に2分割できる。テレビ、スマホ、PCなど分厚い前者に対して、後者を担うのは基本的にOOH(=Out of Home/屋外広告)。あっち[…]
「広く告知する」ことが使命の広告において「あえて潜伏する」「待ち伏せする」ことでメッセージ強度を高められるのはOOH(屋外広告)ならではの醍醐味。ゲリラ戦のように街のあちこちで待ち伏せし、意外なポイントで突如姿を現してメッセージ伝達すること[…]